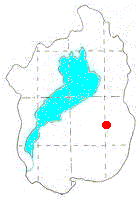1.はじめに 木製のお椀やお盆を手にすると、心が安らぐ感じがします。 木地師とは、とち、ぶな、けやきなどの木を伐り、お椀やお盆などの素地を 作り出す職人さん、を指すそうです。 既報の「さざれ石」を取材したとき、さざれ石を朝廷に献上したのは木地 師であり、木地師の発祥は近江の国(滋賀県)であることを知りました。 そこで、木地師発祥の地を訪ねてみました。 2.木地師発祥の地木地師発祥の地は、滋賀県の 東部、永源寺の奥にあります。 紅葉のきれいな永源寺から、 国道421号線に沿って永源寺 ダムの周りを走り抜け、かつて 銘茶で有名だった政所(まんど ころ)から山道に入ります。
永源寺ダムの周りでは、春は桜、秋は 紅葉を楽しむことができます。 いつも水の枯れたダムばかり眺めてきま したが、今回は満水でした。 ←満水の永源寺ダム 国道421号線から県道34号線に入り、深い山の中を登ります。 人家は途切れ、山を分け入るような感じです。途中、「蛭谷」(ひるたに) という集落があります。ここには後述する「木地師資料館」があります。
蛭谷を過ぎてさらに山道を進むと、 「君ヶ畑」に着きます。 山間の集落で、民家は数十戸ありそう です。 ←君ケ畑の広場 ここは「木地師発祥の地」と呼ばれています。 今から1,100年以上の昔(9世紀後半)、惟喬親王(これたかしんのう) がこの地に隠棲した折、轆轤(ろくろ)で木地を加工する技術を編み出した のが始まりとされているそうです。 惟喬親王は文徳天皇(もんとくてんのう)の第一皇子だったにもかかわら ず、皇位を継ぐことができず、この山奥に隠れ住んだそうです。
出家した惟喬親王が創建したとされる 金龍寺は、村人から高松御所と崇められ たようです。 ←金龍寺(高松御所)に上がる道 ↓金龍寺本堂
.jpg)
金龍寺から100メートル位離れた所に、大皇 器地祖神社(おおきみきじそじんじゃ)がありま す。惟喬親王を祀っている神社です。 ←大皇器地祖神社 ↓
木地師の工房を見学させていただきました。 現在、ここで木地師として工房を構えているのは1軒だけだそうです。 木地師の重要な技能のひとつは、刃物作りにあるようです。丸い鋼材を買い、 自分で鍛冶屋をして「Jの字状」にし、研石で研ぎ出して轆轤鉋(ろくろか んな)を作るのだそうです。
←電動ろくろを回す木地師さん ↓加工材が積み上げられた工房
3.木地師資料館 君ヶ畑へ行く途中の蛭谷に木地師資料館があります。 終点の君ヶ畑まで小さな乗り合いバスが、一日4回、走っているようです。
バス停蛭谷のすぐ横に筒井神社があり ました。 ←バス停蛭谷 ↓筒井神社の石段
.jpg)
石段を上がった所の建物は、扉が閉ま っていました。かつての筒井公文所とい う役所だったのかも知れません。 その後ろに民家風の2階建ての家があり、 それが木地師資料館でした。 ←筒井神社 ↓木地師資料館
資料館は閉まっていました。 実は、11時に訪ねることを電話で予約していたのですが、ここを通り過ご して先に君ヶ畑へ行ってしまったのでした。遅れる旨を君ヶ畑から携帯電話 で連絡しようとしたのですが、圏外ということで通じませんでした。 近くの製材所の庭で煙が少し上っていたので訪ねてみましたが、昼のためか 誰も見当たりません。その横の細い急な道を上り、丘の上にある家で資料館 のことを尋ねてみると、家の奥から出てきた年配の女性が資料館の管理人を しておられる小椋さんでした。 この地域は小椋さんという姓が多いそうです。君ヶ畑と蛭谷は小椋谷と呼 ばれているようです。
資料館の1階は集会室で、2階が展示 室になっています。 手挽きろくろは、軸に巻きつけた紐を 左右の手で交互に引っ張り、回転する木 地を加工するものです。 ←惟喬親王坐像と手挽きろくろ ↓手挽きろくろ
館内には、全国の木地師の作品や、古文書などが展示されています。 古文書としては、木地師加入願、木地師配下願、免許状請書、往来手形、氏 子駈帳、その他がありました。 君ヶ畑の高松御所と蛭谷の筒井公文所は、木地師は自らの氏子であるとし て身分を保証し、職業の繁栄に尽くしたそうです。
←展示室 ↓往来手形
.jpg)
←木地師加入願 ↓氏子駈帳
木地師は、使う木材がなくなると、良材のある土地へ移動したそうです。 そして、全国に散らばった木地師の人別帳として氏子駈帳が作られました。 この氏子駈帳は、単なる統計目的ではなく、お墨付きを与える見返りとして 奉加金などを集金するために利用されました。高松御所と筒井公文所は、全 国の木地師を巡り歩く人を数年毎に派遣した(氏子狩)そうです。氏子駈帳 は、江戸時代初期(17世紀半ば)から明治時代初期(19世紀末)までの 約200年間に亘って更新されたそうです。 4.おわりに 江戸時代に、日野商人(近江商人)は商圏を関東その他まで拡大しました。 日野商人が扱った初期の代表的な商品は木地の椀で、日野椀と呼ばれ、人気 が高かったそうです。 木地師を束ねていた氏子狩の制度は、近江商人の発展とも連動していたの ではないか、と思われます。 木地師は「日本全国の山に勝手に入ってもよい」という免状を持っていた ため、江戸時代には山の8合目以上の木を自由に伐ってよかったそうです。 しかし明治になると、地租改正事業により所有者の許可がなければ一木も伐 ることができなくなり、生業が成り立たなくなったようです。 現在、少ない木地師が各地で伝統工芸の維持に努めておられます。 日本木地師学界という団体が、木地師の歴史、工芸技術などの調査、研究を 進めておられます。 (散策:2008年6月13日) (脱稿:2008年6月30日) 関連記事:1.木地師が朝廷に献上したという伝説の−さざれ石 2.秋に美しい紅葉を楽しませてくれる −永源寺 3.木地師の作った日野椀などを商った −日野商人 参考図書:・木地師‐もう一つの森の文化 日本木地師学会 牧野出版 ・木地師三代 神田 賢一 歴史春秋出版 ・木地師支配制度の研究 杉本 壽 ミネルヴァ書房 ------------------------------------------------------------------
この記事に感想・質問などを書く・読む ⇒⇒ 掲示板この稿のトップへ 報告書メニューへ トップページへ